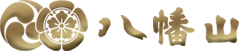祇園祭ブログ
八幡山かわら版
京都・祇園祭の八幡山の話題や行事日程に限らず、京都・祇園祭の様々な山鉾町の様子を写真を交えてご紹介していきます。
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
午後三時より消防訓練が行われました。
八幡山の町会所の前で、消防署の指導を受けながら、消火器の使い方、消火ホースの使い方の説明を受けました。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 15881
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
八幡山では天気が良いと宵山の期間中、山に常飾りを飾り付けます。

Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 14481
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
宵々々山の厄除けのお守りは終わりました。
10時に北観音山のお囃子が終わると八幡山も眠りにつきます。
角の提灯や町会所の提灯を片付けて、暑い一日が終わりました。
また、明日のご来訪をお待ちしております。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 14033
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭

お昼にニ回降った雨も上がり、宵山最初の夜がやってきました。

夜になり、子供達の粽売りの童歌が聞こえてきました。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 10541
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
雨が降るとお山にとって一大事。お山に飾りつけた大切な常の飾りを雨から守らないといけませんから。
雨の匂いがすると町内は臨戦態勢に。雷の音がゴロゴロと近づいてきました。
雨が降り出すとお山から飾りをはずしていきます。はずした飾りは町会所へと運び込みます。
雨が弱い間に無事飾りを取り込めました。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 10272
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
願いかなわず。

カミナリの音とともに大粒の雨が降ってきました。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 10413
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
宵々々山となり、町民総出で飾りつけを行いました。これから四日間天気がいいといいですねぇ。

八幡山の厄除けの粽はお祓いが終わった今日の4時ごろからのお授けとなります。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 10369
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
?曳き初めも終わり、夕方からお囃子の練習が再開されました。今日からは曳山の上での練習です。
提燈に灯りが燈り、幻想的な世界になっています。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 11212
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
7月13日。新町通の鉾と曳山(ひきやま)の曳き初め(ひきぞめ)が行われました。

新町通の四条より上み(かみ:北)では3基の鉾と曳山が同時に曳き初めを行います。南から前祭(さきまつり)の放下鉾、後祭(あとまつり)の南観音山、北観音山です。
写真は北観音山。
「え~んや~らや~~」の掛け声で綱を皆で曳きます。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 11669
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
2006年7月12日。四条通、室町通の鉾の鉾建てが終わり、昼ごろから順次曳き初めが行われました。
写真は長刀鉾。長刀鉾にはお稚児さんが乗っています。
鉾のかじ取り役の車方。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 11559
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
2006年7月11日。13日に曳き初めをする放下鉾の鉾建てが始まりました。
写真はこれから縄組みされる基礎部分です。四本の柱とそれを形作る枠材です。釘を使わずに組み立てられるようになっています。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 11015
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
2006年7月10日。12日に曳き初めをする四条通・室町通の鉾の鉾建てが始まりました。
今日、鉾建てが始まったのは長刀鉾(なぎなたほこ)、函谷鉾(かんこほこ) 、月鉾(つきほこ)、菊水鉾(きくすいほこ)、鶏鉾(にわとりほこ)です。写真は長刀鉾。夜はシートを被されて雨露対策が施されています。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 11127
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
本日行われた「くじ取式」で、八幡山は後祭(あとまつり)の山第二番になりました。
2006年の山鉾巡行順にすべての山鉾の巡行順を掲載しました。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 16513
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
2006年も7月になりました。いよいよ祇園祭のシーズンです。

鉾町ではこれから鉾建てまでの1週間ほどお囃子の練習が毎晩行われます。写真は2つとなりの南観音山のお囃子の練習風景です。7月の練習では軒に提燈が吊るされ祇園祭の到来を告げています。鉾のお囃子が流れるといよいよ厚い夏が到来という感じがしてきます。
※南観音山をはじめ、北観音山、岩戸山は鉾の形をした山なので鉾町と書くとちょっと間違いですが。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 17219
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
7月10日。町会所にて吉符入りの儀式が行われました。
お社の前にお供えをしています。
町内の八幡宮に町内一同参拝をし、お神酒をいただきました。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 12395
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
2006年7月11日。いよいよ祭に向けて京都の町の様子が日々変わっています。
八幡山も町会所のある広場で山建てが始まりました。
写真が増えましたので八幡山の構造のページを更新しました。
八幡山の町内は、明日13日に北観音山と南観音山が町内まで曳き初めに来られます。そのため道路での組み立てが出来ませんので広場で組み立てをしています。
巡行の日には北観音山や南観音山より先に帰らせていただいて、ここへ入って邪魔にならないようにします。
明後日14日からの宵山ではここでちまきや鳩鈴、鳩笛などをお授けいたします。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 13399
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
新町通の曳き初め(ひきぞめ)も終わり、八幡山を道路に出して、埒組が始まりました。
埒が完成すると、非日常の始まりです。道路は通行止めとなり、宵山の三日間はいつもと違う賑やかさがやってきます。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 11189
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
金弊などはいくつかの部品に分かれます。
保存時にばらしていますので、この時点で組み立てます。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 14364
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
14日の午後3時から清祓の儀式が執り行われました。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 16344
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
ラジオカフェの収録が行われています。
町衆の皆さんがラジオカフェのインタビューを受けてます。
http://fm797event.seesaa.net/article/20839752.html
NPO京都コミュニティ放送 JOZZ7AY-FM 79.7MHz
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 14483
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
山鉾町探訪 太子山
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 16478
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
山鉾町探訪 油天神山
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 14784
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
役行者山の修験道者が八幡山へお参りに来られました。
巡行の無事を願い読経。明日は天気が持ちますように。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 13613
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
四条川原町でラジオカフェに遭遇しました。
NPO京都コミュニティ放送 JOZZ7AY-FM 79.7MHz
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 13192
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
23時55分。北観音山の日和神楽が帰ってきました。
年々、帰ってくる時間が遅くなっているようです。お疲れ様です。
北観音山の前に戻って、締めのお囃子を。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 14385
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
巡行の朝。町内総出で飾りつけをします。
どんより曇り空。今にも降り出しそうな気配の中、飾りつけが始まりました。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 12367
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
願い叶わず。雨が降り出しました。
懸装品が濡れないようにブルーシートで雨よけを作りました。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 12977
- 詳細
- 親カテゴリ: 八幡山かわら版
- カテゴリ: 2006年八幡山ブログ 京都祇園祭
何とか飾りつけが終わりました。
合羽も着させて飾りつけが終わりました。ひとまず帰って、裃に着替えて集合です。
Copyright (C) 2006 京都・祇園祭 八幡山保存会. All rights reserved.
- 参照数: 13726
2 / 2